毎年注目を集める「都道府県魅力度ランキング」。2025年版が発表され、今年も全国各地で話題になっています。本記事では、2025年の結果をもとに、過去10年間の推移を比較。上位常連県と急上昇・急落県の傾向から、“人気県の法則”をAI的視点で読み解きます。
都道府県魅力度ランキングとは?評価基準と調査方法をおさらい
都道府県魅力度ランキングは、株式会社ブランド総合研究所が毎年実施する全国調査で、地域ブランドの強さを測る指標として知られています。調査対象は全国1,000以上の自治体。観光地としての魅力、食文化、自然環境、住みやすさ、知名度などを総合的に評価し、全国の回答者が「魅力を感じる」と思う都道府県を順位化しています。
単なる観光人気ランキングではなく、「その地域に関心を持ち、実際に訪れたい・住みたい」と感じる総合イメージを数値化したものです。そのため、各自治体のブランド戦略やPR活動にも影響を与える重要なデータといえます。
【最新】都道府県魅力度ランキング2025年版の結果まとめ
2025年の結果では、今年も北海道が16年連続で1位を獲得しました。以下、上位には京都府、沖縄県、東京都、神奈川県が続きます。上位常連県は観光資源・ブランド力・メディア露出のいずれも高く、安定した人気を維持しています。
一方で注目すべきは中堅県の動きです。富山県や宮崎県、長崎県などが順位を上げており、「地方発の魅力発信」が成果を上げつつあることが分かります。
過去10年の推移から見る「安定上位県」と「浮上した県」
2015年から2024年までのデータを振り返ると、上位常連は毎年ほぼ固定されています。特に北海道・京都・沖縄は「三強」と呼ばれるほど盤石な地位を築いており、国内外の観光客からの認知度も高いままです。
一方で、2020年代に入ってから評価を上げてきた県もあります。たとえば、
- 富山県:北陸新幹線の延伸や、観光ブランド「立山黒部」再評価で注目度上昇。
- 宮崎県:移住支援とメディア露出の増加により「南国リゾート県」として人気再燃。
- 長野県:アウトドア需要の高まりにより、「自然と共生できる県」として再評価。
これらの県は共通して「観光+居住+情報発信」を組み合わせた戦略を展開しています。単に観光地をPRするだけでなく、移住・ワーケーション・地域創生など、複合的な魅力づくりが評価された形です。
魅力度が“上がった県”に共通する3つの法則
AIが過去10年のデータを分析すると、魅力度上昇県には次の3つの共通点が見られます。
① 観光資源の再ブランディング
「新たな視点で観光資源を再発見」する動きが増えています。例として、富山県の“水と山のブランド戦略”や、宮崎県の“アニメ聖地巡礼との連携”など、地元資源を再編集したプロモーションが功を奏しています。
② 移住・定住政策の成功
近年はテレワークや地方移住のニーズが高まり、自治体の支援制度が注目されています。長野や大分などは「移住満足度ランキング」でも上位に入り、魅力度上昇に直結しています。
③ SNS・メディア露出の拡大
InstagramやYouTubeを活用した地域発信も順位上昇の要因です。Z世代の関心を引く「映える風景」「ご当地グルメ」「体験型観光」が拡散されやすく、結果的に地域ブランド向上につながっています。
一方で“下がった県”に見える課題とは?
順位を落とした県の多くは、情報発信力の弱さが目立ちます。観光資源があっても、発信が届いていなければ評価は上がりません。また、都市部と地方の格差拡大も影響しています。特に若年層の流出が続く地域では、地域の元気が可視化されにくく、ブランドイメージが停滞しがちです。
このため、今後は「デジタルを活用した地域発信」や「移住促進×観光政策の連動」が鍵を握るといえるでしょう。
AI分析:2026年に注目すべき“次の人気県”は?
AIがこれまでの推移とトレンドをもとに算出した「次に伸びる県」は次の3県です。
- 富山県:北陸新幹線延伸効果で観光・移住ともに注目度が上昇。
- 大分県:インバウンド需要と温泉観光の復調が後押し。
- 山形県:自然資源と食文化を組み合わせたPRが成功しつつある。
これらの県は共通して「地域のストーリー」をうまく打ち出しており、2026年以降の躍進が期待されます。
まとめ:データが示す「人気県の法則」と地方の未来
10年間の魅力度ランキングを振り返ると、上位県はブランド戦略を継続し、地方県は独自の発信で浮上してきました。AI分析では、今後も「観光+移住+情報発信」の3軸が魅力度向上のカギになると予測されます。
魅力度ランキングは単なる順位表ではなく、「地方の努力の可視化」でもあります。2026年、どの県が新たなスター県になるのか――その行方に注目です。
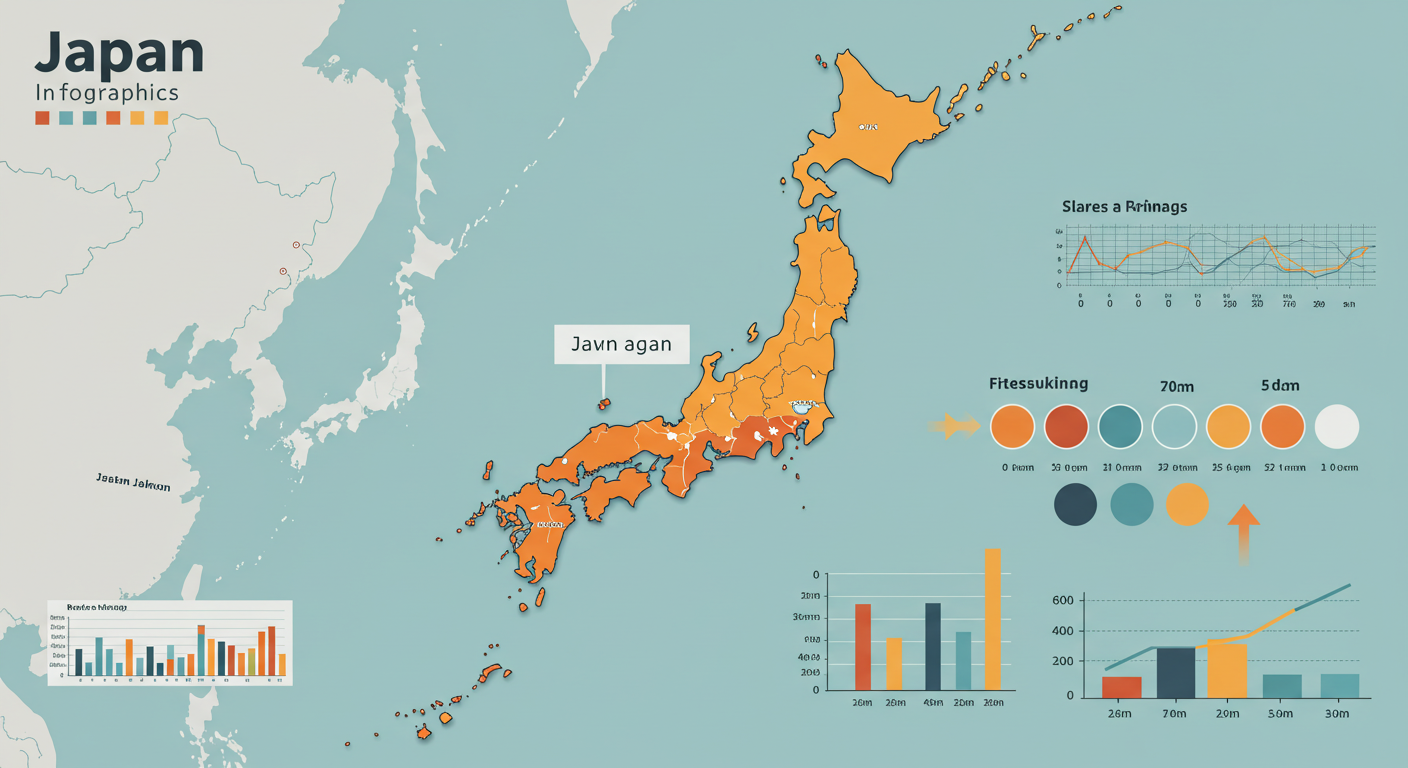


コメント