2025年6月13日、「年金制度改正法案」が国会で成立しました。今回の改正では、高齢化と共働き世帯の増加に対応するため、年金制度にさまざまな見直しが盛り込まれました。中でも注目を集めているのが「遺族厚生年金」の制度変更です。
これまでの遺族年金制度は、配偶者が亡くなった場合に残された側の生活を支える重要な仕組みでしたが、その設計には男女間の格差があるとの指摘もありました。この記事では、2025年の年金制度改正で何がどう変わったのか、遺族厚生年金の見直しを中心にわかりやすく解説します。
第1章:2025年の年金制度改正とは?
政府は2025年5月に年金制度改正法案を国会に提出し、同年6月13日に成立させました。今回の改正は、今後の人口動態や社会構造の変化に対応するためのものであり、厚生労働省によれば「持続可能で公平な年金制度を実現する」ことが目的とされています。
改正の背景には、次のような社会的課題があります。
- 少子高齢化が進み、現役世代が支える年金制度の維持が難しくなっている
- 共働き世帯が増え、従来の「夫が働き、妻が家庭に入る」モデルが崩れている
- 高齢者の単身世帯・子なし世帯が増加している
こうした変化に対応するため、政府は年金制度の根幹をなす部分に手を加える必要があると判断しました。
第2章:遺族厚生年金の制度変更のポイント
◆ これまでの遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった際に、その遺族に支給される年金です。主な支給対象は以下の通りでした。
- 妻(原則として夫に生計を維持されていた配偶者)
- 子ども(18歳まで)
- 夫(障害状態または一定要件を満たす場合)
従来は「夫が亡くなり、妻が受け取る」ケースを前提とした制度設計でした。そのため、妻が先に亡くなった場合や、子どもがいない夫婦で夫が遺族となった場合には、年金を受け取れないこともありました。
◆ 今回の改正で何が変わる?
2025年の改正では、以下のような制度変更が行われました。
- 子のいない夫への遺族厚生年金の支給が拡大
⇒ 従来は子がいない夫には原則支給されなかったが、改正後は一定の年齢や収入要件を満たせば支給対象に。 - 男女の格差是正
⇒ 妻だけでなく、夫も条件を満たせば対等に遺族年金を受け取れるようにすることで、共働き社会に対応。 - 「生計維持要件」の見直し
⇒ 一定の年収以下の範囲で、生計維持関係が認められやすくなる改正も議論対象に。
この改正によって、従来取り残されていた「妻が先に亡くなったケース」や「子のいない高齢の夫」も、公的支援を受けられる可能性が広がります。
第3章:具体的に誰が影響を受ける?ケース別に解説
今回の制度見直しで実際に影響を受けるのはどんな人たちでしょうか。いくつかの代表的なケースで見ていきましょう。
● ケース①:妻が先に亡くなった共働き世帯の夫
共働きで、妻が厚生年金に加入していた場合、妻が先に亡くなると夫は原則として遺族厚生年金を受け取れない仕組みでした。しかし今回の改正で、一定の年齢や収入要件を満たせば、夫も年金を受け取れる可能性が生まれました。
→ 夫婦が共に働いている世帯にとっては、大きな安心材料になります。
● ケース②:子どもがいない高齢夫婦
これまでは「子がいないと夫は遺族年金を受け取れない」ことが多く、老後の生活に不安を抱える人も少なくありませんでした。改正後は子がいない場合でも、高齢や経済的条件によって支給されるようになるため、支援が広がります。
● ケース③:単身高齢者や独身者
遺族年金の対象外である単身者や独身者には直接的な影響はありませんが、今後の制度改正ではこうした層への新しい支援制度が議論される可能性もあります。孤独死や生活保護との関連も視野に入れて、今後の議論を注視する必要があります。
第4章:今後の年金制度とライフプランの考え方
年金制度は今後も少子高齢化に応じて見直しが続くと予想されています。今回の改正はその第一歩であり、以下のような方向性が示されています。
- 受給開始年齢の柔軟化(70歳以降の繰り下げ推進など)
- iDeCoや企業型DCなど自助努力型制度の拡充
- 「マクロ経済スライド」の調整による年金額の維持・抑制策
こうした動きに対応するためにも、公的年金だけに依存せず、NISAやiDeCoを活用した資産形成が重要になります。政府もこれらの制度の普及を後押ししており、自分自身で備える意識が今まで以上に求められています。
まとめ:2025年年金制度改正を前向きに捉えるには
今回の年金制度改正、とくに遺族厚生年金の見直しは、男女平等や多様な家族形態を尊重した制度への一歩です。制度の変化は不安を呼びやすいものですが、情報を正しく理解すれば「自分たちの生活にどう影響するのか」が見えてきます。
対策としておすすめなのは以下の3点です。
- 厚労省や日本年金機構の公式発表を定期的に確認する
- 将来に向けたライフプランを家族と話し合っておく
- 必要であれば、社会保険労務士やファイナンシャルプランナーに相談する
制度は変わっていきますが、正しい備えをしておくことで、安心した暮らしを続けることは可能です。
参考リンク
- 厚生労働省「年金制度改正法について」
第178回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)の開催について - 日本年金機構「遺族年金について」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izoku/

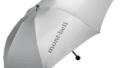

コメント